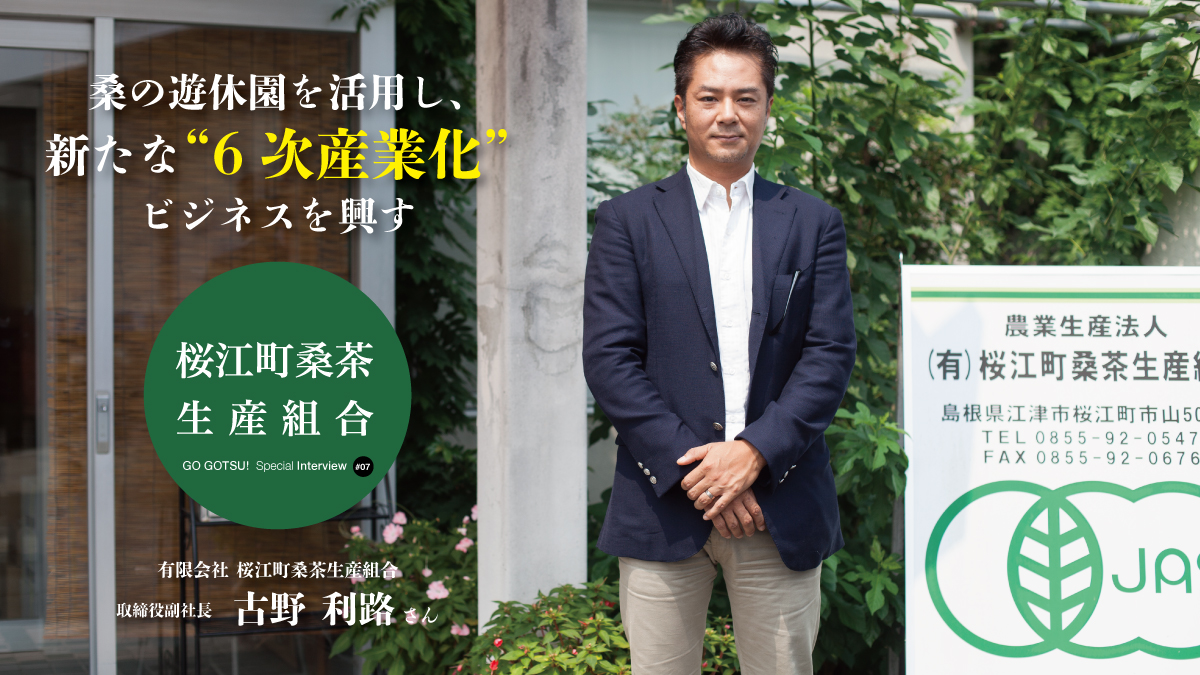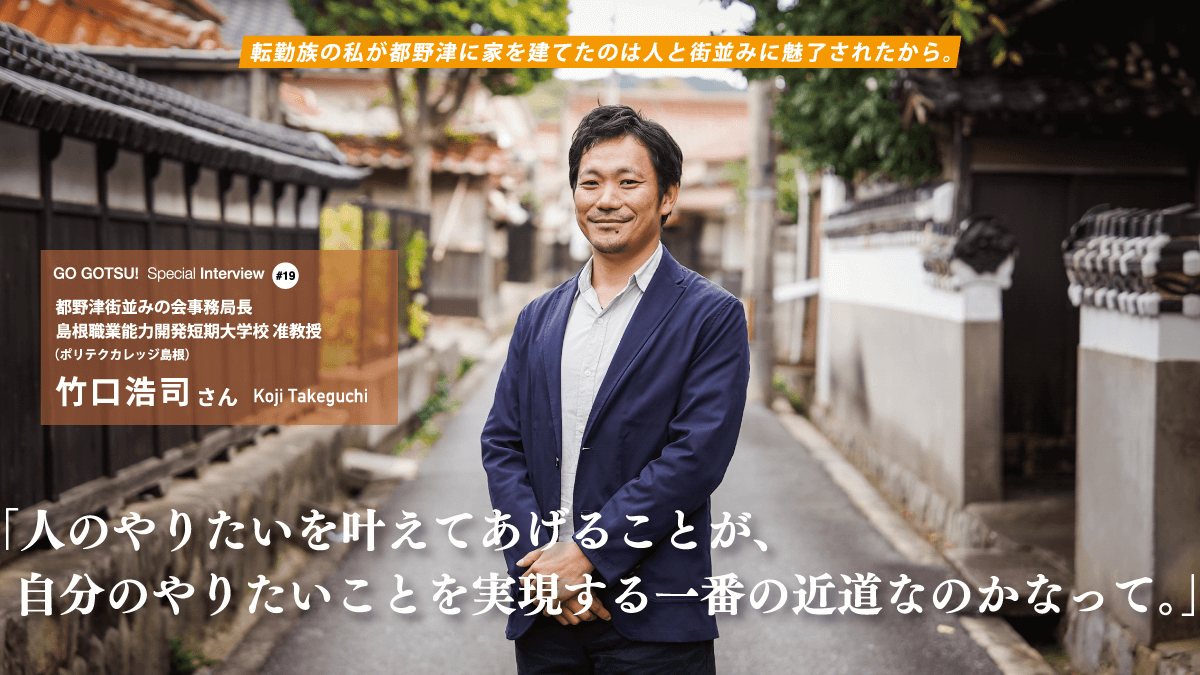どうしたらお母さんたちに伝わるか、どうしたらもっとお母さんが楽しく育児できるか、ということを考えるのがテーマですね。
自分で自分のことを知って、自分は今の自分でよかったなと思ってもらいたいし、私はそこに関わりたい。
〈Vol.21〉2025年3月7日
杉井 美保さん
ー Miho Sugii
ー 助産師(マタニティハウス花)
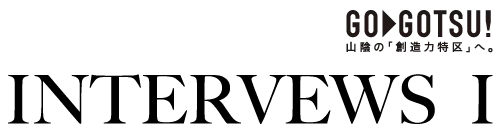

取材・文・写真
戸田コウイチロウ〈GO GOTSU.JP編集部〉
私の仕事は、まずはオギャー!って産まれた赤ちゃんのお世話から思春期、更年期の相談 、妊娠、出産、育児の相談、性の相談、と女性のいろんなライフサイクルの中で起きる変化のポイントに携わるような職業なんです。
江津市には分娩ができる医療施設は残念ながらゼロだ。そのため、浜田市や大田市、あるいは出雲市などの医療施設までの移動を余儀なくされる。江津市の令和6年4月から令和7月2月までの出生数は82人。(島根県政策企画局統計調査課による公表データより)。少子化は著しく、この状況であれば市内に分娩可能な医療環境を整備することは難しい。
今回お話しを伺ったのは、2022年度の江津市ビジネスプランコンテスト「Go-Con」に出場し、翌年に嘉久志町の住宅街に産後ケア施設「マタニティハウス花」をオープンさせた助産師である杉井美保さん(以下、杉井さん)。日帰りでの利用はもちろん、宿泊ケアも提供されていて、お母さんの着替えや育児用品を備え、なにより杉井さんの手料理による温かい食事も用意される。
杉井さんは長らく愛知県小牧市で助産師として仕事をしてきた。仕事を通じて様々な経験を重ねていく中で、どうして江津にUターンしようと考えたのか。Uターンしてからの江津での暮らしと仕事は自身をどのように変化させたのだろうか。どんな想いでこの場所をつくったのだろうか。先に出生率についてお伝えしたが、事業として成り立つ分野なのか、産後ケアとはどこまでの領域の仕事なのか、早速お話を伺った。

▲白を基調したモダンな外観。とてもリラックスできる空間だ。
杉井さんのご職業について聞かせてください。助産師、産後ケアとはどのようなお仕事なのでしょうか?
杉井さん:私の職業は助産師です。産後ケアを中心に色々なことをさせていただいています。お産をした方達と向き合い伴走していく必要があると考えています。本来は妊娠する前に小・中・高学校あたりから、女性の体がどういう風にできているかを知り自分の体を大事にすることが大切でその年代の方々とも関わりたいのですが、今は産後の方や、出産世代の方たちを中心に関わっています。
産後ケアは出産後のお母さんたちの疲労回復のためのケア、心配事の相談、ときには愚痴を聞いたりもしています。産後は社会的な隔たりを感じるお母さんもいらっしゃるので、ここに来て色々な話をしてスッキリして帰られたりしますね。
それと出産後は赤ちゃんが泣くので自分のことは後回しになってお昼ご飯が質素になりやすい。そんなときはここで温かいご飯を食べてリラックスしたり、赤ちゃんとしっかり向き合うということを中心に行なっています。
好きな自分で思春期を迎えるために、元気に妊娠・出産されるために、楽しく更年期を過ごすために年代問わず、小さなうちから「性」というものについて理解し自分の体を大事にすること。これが今の江津にとっても大切なことですし、ここに来たらそういったことがわかるというイメージの場所にしたいと思っています。
助産師というお仕事はどこからどこまでのことをやるのでしょうか?
杉井さん:そこからですよね(笑)。まずはオギャーって生まれた赤ちゃんのお世話から思春期に至るまでの性の相談、月経の相談、更年期の相談、それから妊娠、出産、育児といった女性のいろんなライフサイクルの中で起きる変化のポイントに、ちょっとずつ携わるような職業なのかなと思っています。
赤ちゃんが産まれる現場にいるだけではなく、もっともっと広い領域にまたがって専門性が求められる職業なんですね。
杉井さん:もっともっと広くて、もっともっと深いんだと思います。多岐に渡るので助産師さんによっては育児とかおっぱいとか専門でやっていらっしゃる方もいますし、もちろん病院でお産専門で働いている方もいます。そこだけではなくて、そこに辿り着くまでの成長過程だったり、そこを終えた後の更年期の方までを含めて私たちの仕事としては捉えられているので、あらゆる女性のライフステージの変化に携わるのが助産師ということですね。
助産師になるためには、高校を卒業して大学に行くか、専門学校に行って看護師の免許をまず取ります。その後に助産過程に進みます。ちょっと面倒なのかな(笑)。私はこの仕事をずっと続けていますね。
杉井さんは愛知生まれ、江津育ち。江津市で社会人として多くの時間を過ごした。しかし、そこで助産師でありながらも助産師だけの仕事ができないことについて自問自答するようになった。自分自身の助産師としての技量、これまでのキャリアを振り返ってどれくらい自分は成長したのだろうか、助産師としての自分はどんな風に受け入れられるのだろうか、もっとレベルが高いところに行った時に自分はどのあたりにいるのだろうか、どれくらいのことがやれるのだろうかと考え始めるようになる。
そのような自分への問いに対して「あやふや」だったことに真摯に向き合い、改めて助産師という仕事にしっかり取り組もうと決意する。
杉井さん:同じところ(江津の医療機関)にずっといたわけですよね。「私って実際はどこまでやれるんだろう?」と思いながら仕事をしていました。「ある程度のことはやれるだろう」と。今思えば間違った認識を持っていたことに気づくんですけど。
ちょっと外へ出れば、誰も自分のことも、自分のスキルのことも知らない。私自身愛知で働いて、世の中を知らないことや、もっともっと経験しなければいけないことがたくさんあるんだなということを思い知らされましたね。
「ああ、やっぱり井の中の蛙だったんだな」って。そこでもっと勉強して助産師としていろんなことを知って、経験していきたいと思ったんです。その後、色々な経験を積む中で、そろそろスキル的には満足かなという時期になった頃に(江津に)帰ろうかなと思ったんです。自分の子どもたちの進学も重なる時期でもあったし、よく言う話ですけど、一度外に出ると魅力を感じなかった江津に魅力を感じるようになるというか。そういうことがUターンの主な理由ですね。

▲自分を振り返りながらより一層邁進していくことを江津にUターンする前に決めた。
初めて勤めたクリニックで1年ほど働いた頃、ある専門学校で助産学科を新設するにあたって教員を募集していることを知り、応募。臨床経験が5年以上あった杉井さんは教員資格を満たしている。1期生から関わることも自身にとってチャンスだった。採用され、教員として働いていく。実習・実践の楽しさだけでなく難しさも経験し、教員として「教育とはなにか」を考える時期でもあった、と振り返る。
その後、新たに新設されるクリニックからの誘いがあり転職。施設の立ち上げ、開業を経験しながら助産師としての軸はブレることなく着々とキャリアを積んでいった。子どもの大学進学と小学校進学という節目のタイミングで「戻るなら今だ」と思い、2018年に江津にUターンした。
江津に戻ってから、すぐにお仕事をされたんでしょうか?江津を出たときとは違う魅力を感じたとのことですが、それはどんな景色だったんでしょうか。
杉井さん:江津に戻ってからは済生会江津総合病院で働いていました。自然がやっぱりいいなと思いました。子どもたちも伸び伸びしているんです。例えばなんですけど国道9号を走っているときに「道が1本っていいな」って思う時があるんです。すれ違うときに誰かに気づくから。向こう(愛知)にいるときは道が多いし、人も多いからそういうことがないんですよね。運転していて子どもを見かけた時に子どもが大人に見守られているな、幸せだろうなって思うんです。
それから都会だと子どもを産む人数は一人というのは珍しくないんです。でも江津だと4人兄弟とかいるわけです。1学級で一人っ子って意外に少ない。江津は子育てがしやすいんじゃないかって思ったんですね。産む年代の数は少ないけれど、ひとりの人が産む子どもの数が多い。向こうから帰ってきて余計にそう思います。江津市役所の子育て支援課さんともそういう話は出ますね。産む年代が増えたらもっと人口増えるんじゃないかなって思うんですけど(笑)。
子どもを産む年代というのは広がっていないんですか?若い世代はもちろんですが、最近は高齢出産の「高齢」の年齢が上がっているようにも感じます。
杉井さん:40歳で初産(ういざん)のようなケースは愛知では割と普通でした。江津は結婚も早いし、若い年齢で産む女性が多いですよね。20代で2人目のお子さん、という方もいらっしゃる。逆に40歳で初産というのは少ないように感じますね。
先ほどの「江津の子育てのしやすさ」というのはどのようなときにそう思ったんでしょうか?
杉井さん:人口が少ないこともありますが、まず待機児童がいないこと。それから共働きの家庭が多いと思うんですけど、育児もそれなりにきちんとしている印象はありますね。児童クラブがあったりだとか、子どもを見てあげられる環境が整っているなと思っています。
都会は待機児童問題があるし、第3子、第4子だとなかなか園に入れないことも多いんです。働きたいと思った時に、子どもを見てもらえる環境が江津にはあることが「子育てしやすいまち」と感じています。

小中高世代に向けて「性」について話したり、学ぶ機会をつくったり、私たちの仕事や活動の幅ってみなさんが思っている以上に広いんですね。
事業性というところで率直な質問をさせてください。近年の江津の出生数は年度単位で言うと100人程度ですよね。これからどんどん増えるともなかなか考えにくい。そのような少子高齢化の地域社会の中で「助産師」「子育てに関わる職業」という意味において、事業性や将来性についてはどのようにお考えでしょうか?
杉井さん:今は江津がフィールドで、子どもの数は確かに減っています。ただ、私の考えでは、産後のケアということでいえばそうなのかもしれないのですが、例えばこれから更年期の方が増えたり、先ほども言いましたが、小中高世代に向けて「性」について話したり、学ぶ機会をつくったり、私たちの仕事や活動の幅ってみなさんが思っている以上に広いんですね。
企業助産師ってご存知ですか?地域の企業に入っていって、そこで働く女性の月経の悩みだったり、不妊治療をされている方や更年期世代の方のいろいろなサポートだったり、家庭でできる性教育の話をするといった業務が、都心部ではすでに始まっているんです。そういうことも私はこれから展開していきたいと思っています。子どもの数だけを見るというよりは、やれることはたくさんあるという風に考えていますね。
他にも例えば性犯罪やデートDV(※編集注:交際相手からの暴力行為。精神的なものや性的なものも含まれる)についても警察は「これをやると犯罪なんだよ、いけないことだよ」という言い方中心になりますけど、助産師の場合は「性」や「心」の要素を入れ込んだ上でこの職業ならではの立場でデートDVの話ができます。切り口が変わるから伝わり方も変わっていくんですね。助産師ならではの立場で、できることがあるので活動の幅を広げていけると思っています。
江津の中での対外的な業務の連携や関わっている取り組みなどはあるんでしょうか?
杉井さん:(地域の)保育園に「保育園でできる性教育ってなんだろう?」というような投げかけをしています。園児が自分で自分の体を守ることや大事にすることを学ぶ土台になるようなお話をさせてもらったりしています。養護学校では「性」や「性犯罪」の話をさせてもらったり、高校でも同様に話をさせてもらっています。今度「親子で聞く性の話」ということを学校でやることにもなっていますし、結構あちらこちらで活動しているんですよ(笑)。大事にしているテーマは「自分の心と体にどう向き合うか」ということですね。
「フェムテック(Femtech)」という言葉がある。月経や出産、不妊、更年期など女性特有の健康課題にはサポートが必要であるということからオンラインカウンセリングやアプリを使って健康(体調)管理するといった「フィメイル(女性)」と「テクノロジー(技術)」を掛け合せた造語だ。
女性にとって自身の健康やライフイベントに関する悩みごとを誰かと共有するということは誰もができるわけではない。ひとりで我慢せず、誰かに話そう、みんなで助け合っていこうとするムーブメントだ。共働きにせよ、あるいはシングルにせよ、子育てには「大変さ」がつきまとう。地域社会や企業が、それらを受け入れながら働きやすく、暮らしやすい環境をつくり、女性をサポートしていこうという概念だ。特に、これからは男性こそがこのような社会の動きを知っていくことも大事なはずだ。これまでの杉井さんのお話は、このような概念が背景にあるように感じるが、杉井さん自身、どのような理念や江津における問題意識を持っているのかお聞きしたい。
杉井さん:自分のカラダのことを知らなさ過ぎる、ということはまず問題かなって思いますね。例えば、女性であれば月経の始まる時期というのもあります。「始まったね~。そのときはこういう風に処理するんだよ~。」という話を子どもたちにはするんですけど、果たしてそれがなぜ起きるのか、どういう風にカラダが変化すると(月経が)近くなってくるのか。併せて「あなたのカラダはこういう風になっているんだよ」というところがすっぽ抜けていて、事象に対してだけでしか伝えられていない。
これは文部科学省や厚生労働省の関係もあるのかなとも思いますし、全国的にそういう傾向だろうと思うんですけど、学校でやりにくいのであればご家庭だったり、ここ(マタニティハウス花)でも十分できることです。ここは宿泊機能もありますし、そういうときにゆっくり時間を使ってお話する術があると思っています。
更年期についても然りです。年齢が上がっていくから更年期になるという理解だけではなく、もっと前からカラダはこんな風に変化していくんだっていうこともお伝えしたいんです。そうやって大人が理解しなければ子どもにも伝えていけないですよね。自分のカラダのことを知らない人は本当に多い。自分のカラダのことを知って心構えができていけば、いろんなことに対処できていくんじゃないかなって思うんですね。
妊娠も同様です。「どんな風にカラダが変わるの?」「ホルモンバランスは?」「なぜ、つわりが起きるの?」こういうこともすべて自分のカラダのことですよね。「なぜ?」を知ることによって、その人が良い方向になるようにお役に立てたらいいなと思ってやっています。

男子生徒向けに月経の話や生物学的な男女の違いの話などをしに行くんです。お互いに違いがあるから、痛みや苦しみがわからないのは当然です。でも、思いやることはできますよね。
男性にとって女性の生理現象のことは、どこか他人事って感覚があるように思うんですね。でも、例えば家族であるなら相手(妻/パートナー)の健康状態が、今どんな状況にあるのかを理解することは、とても大切なことだと思いますね。
杉井さん:まさにこれから開催するイベントがそういう趣旨なんです。学校で開催するんですけど、女子高生が考えた企画で同じ学年の男子生徒に「私たち女性は(月経のときに)こんなに大変なんだよっていうことをわかってほしい」という講演依頼があったんです。だから今度、男子生徒向けに月経の話や生物学的な男女の違いの話などをしに行くんです。
お互いに違いがあるから痛みや苦しみがわからないのは当然です。男性が股間を蹴られたときの痛みを女性がわからないように男性も月経の痛みはわかりません。でも、思いやることはできますよね。
学校での一コマでは「そんなとき、男子に何ができるのかを考えてみようか」っていう内容です。生理用ナプキンなどの小物も持っていって、理解してもらって「今後パートナーができたときに役に立つよね」と思ってもらえるような話ができたらいいなと思っています。わからなくても共感できる関係ができたらいいことですよね。

▲地域の学校に招かれての授業・講演活動にも積極的だ。(写真提供:杉井さん)
2022年度の江津市ビジネスプランコンテスト「Go-Con」にエントリーし、最終選考まで進んだ。その後、2023年に「マタニティハウス花」を嘉久志町にオープンした。
花はOHANA。読みは「花(はな)」。 OHANAはハワイ語で「家族」を意味する。「利用される方を家族と思ってケアしたい」という想いを込めた。ロゴのモチーフは母性愛である百合のデザインだ。ここまでのところの手応えはいかがだろう。
杉井さん:ビジネスプランコンテストは多くの人に知ってもらえる機会になるところがいいですよね。「私、こういうことをしたいんです」ということを。それから、自分自身「私は、これをやりたいんだ」という気持ちを確認ができるところもいいですね。
江津に戻ってきたときに「産後ケアできるところがないじゃん」って思ったんです。出産の思い出だったり、家族のイベントだったり。そういった、これまで江津にないものをつくりたいって思うようになりました。マタニティアートをしてもらったり、写真を残してもらったり、私自身も妊婦のときにやってよかったなって思ったことなので、今度は私がやってあげたいなって。
田舎でもこんなことできるよ、体験できるよっていうことをやりたかったというのが一番ですね。講演でも児童や生徒に『田舎だからとあきらめないで。江津にはいいとこいっぱいあるよ』という話をしています。
手応えとしては、江津から産後ケア事業の委託を受けているので利用しやすくなっているということと、宿泊ケアがあるという安心感が少しずつ広まってきているかなと感じるところです。それとですね、愛知にいる頃の話ですが、都会では出産を迎える人が40代あたりも多いですよね。高齢じゃないですか。そうなるとご両親も高齢です。だからお孫さんを預かりにくい環境なんです。
江津に帰ってきて思うのは、こちらは若い世代でお産をされても、ご両親は働いている世代。日中は預けることはできないし、実家に戻っても、なかなか面倒を見てとは言いにくく、遠慮がちになるという話を聞きます。食事も前日の残りを食べるとか、乱れがち。そういうとき、ここを利用してもらいたいんですね。温かい食事をご用意できますし、宿泊中は夜中呼ばれればいつでもお手伝いしますし、ある意味で助産師を独り占めできる贅沢な時間を過ごせるわけです。
今の情報を得ながら産後や子育ての環境ができる場所としてはいいかなと思っています。退院された後、ここをたまに使うことで「すごくカラダが楽になる」とおっしゃる方もいます。
オープンして1年ちょっと(※取材時)だから、まだあまり課題とか問題意識のようなものはほとんどない段階でしょうか。
杉井さん:初めて赤ちゃんを抱っこするのが「我が子」なんてことが増えているんですよね。なぜなら子どもが周りに少ないから。オムツを替えたこともないし、首の支え方ひとつわからないお父さんお母さんが育児をスタートするんですよね。きっと不安だらけだし、大変だと思うんですよね。そこにサポートは必要です。その子が、1ヶ月後どんな生活になるのか、2ヶ月後にどんな生活リズムになっていくのかまでは、なかなか予測できません。
そういった、ちょっとした不安を抱えたまま育児がスタートするので様々なアドバイスが必要になってきます。利用された方を想いながら「今頃ちゃんとできているかな、大丈夫かな」なんて思いますね(笑)。
今の若い世代の人の中には、具体的に「こういう時にはこうするんだよ」「これはやってはいけないよ」といった感じでわかりやすく伝えてあげないと、なかなか理解できないということがありますよね。自分で「こういう感じでいいかな」「これで大丈夫だから、このままやっていこう」という風に考えられる人は少ないように感じています。「こういう時はどうしたらいいですか?」みたいな質問がありますが、必ず答えが欲しい、そうでなければ不安になる、という傾向があるように感じます。SNSを見て不安になるお母さんは結構多く、自分で判断ができないんでしょうね。昔だったら「これくらいなら大丈夫よ」とか言ってくれる周りのおばあちゃんがいてくれましたよね(笑)。
最たる例は、離乳食がはじまる段階のとき。テキスト(育児本)に書いてあることが絶対だと思っちゃう。食べない子もいれば、もっと食べる子もいる。テキストに書いてあるグラム数は絶対じゃないですよね。子どもを見て判断するのではなく、テキストを見て判断する。食べる時間だって子どもによって差はあります。そういう育児をしている親が多いからこそ、ここを一回挟んでもらえれば考え方に幅を持たせてあげられるんですよね。どうしたらお母さんたちに伝わるのか、どうしたらもっとお母さんが楽しく育児できるのか、ということを考えるのがテーマですね。

どの年代の人たちも楽しく生きてほしい。下を向くんじゃなくて、自分で自分のことを知って、自分は今の自分でよかったなと思ってもらえるようなポイントをひとつでも発見してもらいたい。
もう少しジェネレーションについてお聞きするのですが、都市部で長く働いていた経験から見て今の江津の20~30代の若い世代にはどんなイメージを持たれていらっしゃいますか?
杉井さん:とげとげはしていないですよね(笑)。向こう(愛知)はキャリアウーマンが多いわけですけど、働いてきた時間が長い分、自分のリズムができていますよね。高齢になって出産すると、これまでの自分のリズムから、なかなか赤ちゃんのリズムに変えられないというケースはよく見てきました。「赤ちゃんこんなに泣くけど、夜寝たいんだけど、私。」みたいな。
そういう意味では江津の人の方が柔軟性はあるし、それは若いうちから子どもを産むという心構えがあるからなのかわかりませんけど、印象としてはそんな風に思いますね。育児休暇は浸透してきていますが、それでも都市部にいるキャリアを崩したくない女性は「早く仕事に戻りたい」という意識が割と高いと思います。
どの年代の人たちにも楽しく生きてほしい。下を向くんじゃなくて、自分で自分のことを知って、自分は今の自分でよかったなと前を向ける様に思ってもらえるようなポイントをひとつでも発見してもらいたいし、私も関わりを持たせていただきたいと考えているんです。そういうことを感じることが毎日のようにあります。例えば育児がつらい、とか思ってほしくなくて。
私が性教育の話をするときの内容ですけど、まず生まれてきたこと自体が奇跡だということ。こんなに大きくなれたことも奇跡なんです。精子と卵子が出会う瞬間から奇跡がありますよね。それを意識せずになんとなく生きてきてしまう。自分自身が奇跡の人だからこそ、自分自身を大事にしてとか、もっと自分を愛してあげてって思うんです。「社会がいやだ。」「人間関係がいやだ。」ってずっと思い続けてしまうのは・・・ちょっと寂しいなって思うんです。
UIターンして何か事業や活動を始めたり、起業するタイプの人は、いわゆる自己肯定感や自己実現欲求が高い傾向にあると言えそうだ。そうかといって地元で暮らし、働き、楽しみを見つけながら自身をより良くしていこうと活動する人だってこのまちにはたくさんいる。
江津が掲げるスローガン「GO GOTSU! 山陰の『創造力特区』へ。」は、このまちで暮らす誰もが、自由に、好きなように、創造的に生きる権利を持っていることを表したものであり、そんな気持ちを持った人が増えていくことでまちをより良くしていきたいという想いと願いが込められている。
クリエイティビティを持って暮らす、生きるとは一体何だろう。あなたにとっての創造力とはどのようなことを指すのだろう。これを最後に杉井さんにお聞きしたい。
杉井さん:江津って小さなまちで、人口も減っていく中で、それでもプロフェッショナルな人たちが多いまちだと思っているんです。いろんなことに特化した人がたくさんいるなって。
人生諦めてしまったら終わりで、私の話だったら「私はここで何ができるだろうか」「助産師として江津にどういう関わりができるだろうか」ということをいつも考えながら仕事をしています。そうしているとワクワクが生まれてきます。
そのワクワクが形になった時にすごく楽しくなって。それでもすべて成功するとは限らないじゃないですか。そんなときに「なんでできなかったんだろう。」「じゃあ次どうしていこう?」と考えることもワクワクするんです。そういうことを形にできるのが江津、と思っています。助けてくれる人もたくさんいるから、私もアクティブに動けるんだなって感じています。
GO GOTSU! INTERVIEWS #21
MIHO SUGII